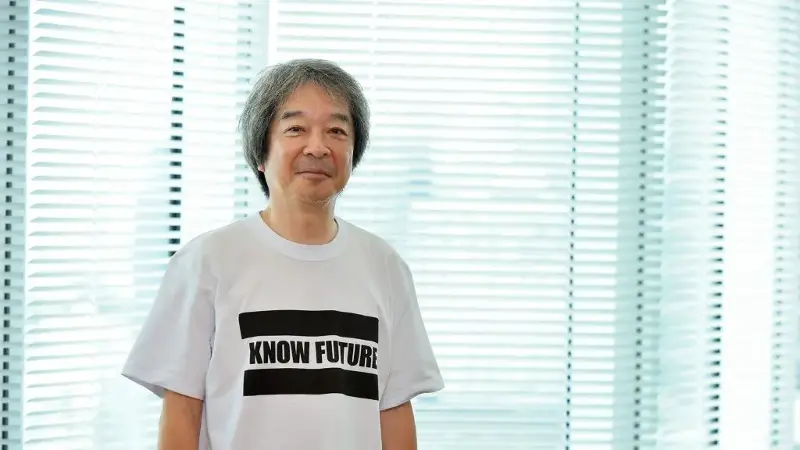
- ZOZO NEXTが運営する「fashion tech news」は、ファッションとテクノロジーの接点を発信するオウンドメディアとして成長を続けている。
- なかでも、素材や技術の深掘りする「RESEARCH」と、ブランドや製品の文化的背景を伝える「CULTURE」のカテゴリーが人気。
- 中立性・専門性を重視した発信を軸に、「第一想起されるファッション専門メディア」をめざして取り組みを強化している。
ZOZOグループの先端技術や研究開発を担う株式会社ZOZO NEXT。その情報発信を担うのが、同社が運営するオウンドメディア「fashion tech news」だ。直近、このオウンドメディアはPV数3倍、UU数1.3倍と急成長を遂げ、現在は月間PV数が平均で約250万、UU数がおよそ65万を記録。記事コンテンツを主軸とする企業オウンドメディアとして、きわめて高い成果を上げている。
「研究成果を中立的に発信することが我々の責務であり、同時に企業ブランディングにもつながる」という信念を話すのは、同オウンドメディアを率いる編集長の玉井泰史氏だ。
「fashion tech news」が読まれるメディアへと変化した背景や、日本の技術と文化を届ける新たな挑戦、そしてオウンドメディアのあり方について、玉井氏に話を聞いた。
◆ ◆ ◆
研究者目線から生活者目線へ、メディア方針を転換
――「fashion tech news」は、PV数を3倍に押し上げるなど、直近で大きく成長したオウンドメディアという印象です。何を変えたのでしょうか?
「fashion tech news」は立ち上げ当初、アカデミックな記事を多く扱っており、ファッションを研究する人や業界内の限られた読者層に向けて発信をしていた。ファッション関連素材や技術などがテーマの記事も、それが実際にどういったプロダクトに使われ、どのような人気を得ているかといったユーザー視点の情報は重視していなかった。
そうしたなかで近年、「技術や素材の動向というものは本来、一般ユーザーにとっても有益な情報であるべきだ」という考えのもと、生活者目線のコンテンツ作りに方針転換した。
取材・編集の際は、ワンプロダクトの機能を徹底的に掘り下げ、専門誌に負けない情報量でまとめることを重視している。たとえば、アウトドアウェアやランニングシューズを扱う際は、厚みや構造を数値や比較データで示し、グラフや写真も活用する。その一方で専門用語はできるだけ減らし、読む側が理解しやすいよう噛み砕いたコンテンツに仕上げるようにした。
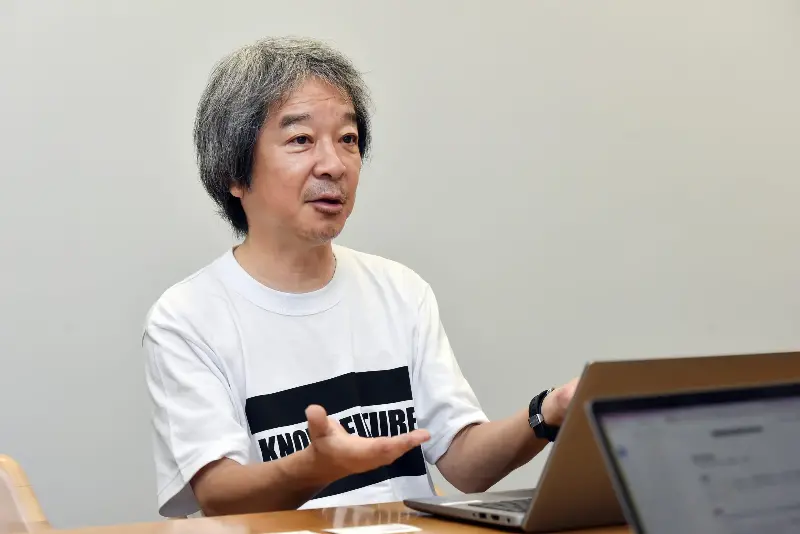
玉井 泰史/ZOZO NEXT fashion tech news 編集長。ファッション誌などの編集を経て、2019年に株式会社ZOZOテクノロジーズ(現、ZOZO NEXT)に入社し、現職。
――読者のターゲットを専門家から一般ユーザーへと広げたことで、コンテンツ制作の方針にはどのような変化がありましたか?
従来の(ファッション)素材単体のみの話から、具体的なプロダクトやその機能、人気の背景といったストーリーに焦点を当てるようになった。それにより、読者の生活に直結するような内容となり、一般読者にも受け入れやすいコンテンツになったと考えている。
一方で、快適性や機能性といった観点で衣服の進化が専門家以外にも注目されるようになったのも追い風だった。ファッションにおけるテクノロジーの役割が一層明確になったことは間違いない。
技術と文化で深掘る、独自のコンテンツ設計
――「fashion tech news」のなかで、人気あるいは特に注力しているカテゴリーは何ですか?
「RESEARCH」、「CULTURE」という2つのテーマが人気だ。「RESEARCH」は素材や機能を深掘りし、「CULTURE」はブランドやプロダクトの歴史・文化的背景を紐解く役割を担っている。技術と文化の両面からファッションテックを捉えていることが特徴だ。
「RESEARCH」カテゴリーは、従来の「fashion tech news」を象徴するコンテンツで、専門性に力を入れて制作を進めている。一方で「CULTURE」カテゴリーでは、誰もが知るブランドや製品の背景をたどり、歴史や文化の流れから「なぜ今人気なのか」を示すことで、新たな発見を読者に提示している。このカテゴリーは、多様な読者にとって読みやすいテーマであり、それでいて新たな気づきをもたらす魅力あるカテゴリーだ。ファッションテックの表面的な情報だけでなく、その裏にあるストーリーを伝えることがメディア全体の厚みを支えていると考えている。
――質を維持しながら読者との関係を深めるため、どのような工夫をしていますか?
1日に2〜3本の記事を公開しつつ、外部ライターとも連携して取材密度を担保している。また、会員登録機能、記事読み上げ機能、メルマガ限定コンテンツなどを導入し、リピート率の向上にも努めているのが現状だ。メルマガの開封率は非常に高く、新機能も今期中に追加予定だ。こうした継続的な改善を行い、ユーザーとの信頼関係を強化している。
また、英語版を約2年前にリリースし、国内在住の外国人や海外の読者にも記事を届けられるようになった。英語版記事がバズるケースも出てきており、PV数の向上を後押ししている。それらは、日本語記事を生成AIで翻訳し、最終的に翻訳会社がネイティブチェックを行う流れで品質を担保している。
――「fashion tech news」の活動のなかで、「Artisan」(アルチザン)というプロジェクトも進めていますね。これはどのような経緯で始まったのでしょうか?
「Artisan」は、ZOZO NEXTが推進する「機能性と美を兼ね備えた新素材の開発プロジェクト」から着想を得て立ち上げた。そこには、伝統工芸の現場が抱える後継者不足などのさまざまな課題を解決したいという想いと、日本の伝統技術を進化させ広く発信したいという願いがあった。その両方の想いが重なり、日本工芸の『再評価』と『再活性化』をめざしてWebコンテンツの制作が始まった。
現在は従来の工芸の枠を超えた実験的プロダクトを紹介し、その背景にある産地や職人のストーリーを丁寧に紐解いたコンテンツを公開している。結果として年齢層の高い読者から支持を得ており、社会的課題の解決を視野に入れたコンテンツとして評価されている。
「Artisan」では動画コンテンツも制作
めざすのは「第一想起されるファッション専門メディア」
――Webメディアという形でのオウンドメディア事業を維持することは簡単ではありません。「fashion tech news」が継続している理由をどのように考えますか?
当社の方針を体現し、一次情報を中立的に届けるという軸をブラさないことで読者に信頼されているのが大きな要因ではないだろうか。それによって、直接的な売上貢献はなくとも、ファッションテックの社会的意義や価値を伝えるというミッションを果たせていると思う。技術紹介の記事を見た企業・団体から声がかかるケースもあり、メディアを通して事業の波及効果を生む土台にもなっている。
(自社のPRにつながるようなコンテンツが中心の)一般的な企業のオウンドメディアとは異なる、独自の視点とアプローチで運営していると感じる。「世の中にあるファッションとテクノロジーの情報を発信し続ける」という方針も明確で、宣伝より公共性を優先できていることも我々の特長だ。
たとえば当メディアでは、新商品の情報だけでなく、その背景にある開発ストーリーや担当者の想いも丁寧に取材している。プロダクト開発者やプロジェクト責任者などへの徹底した取材を通じて、一次情報に基づいた深度のあるコンテンツを追求している。
――「fashion tech news」の今後の目標について教えてください。
ファッション専門メディアのなかで「第一想起される存在」になることを目標に掲げている。編集長としてその方針を常に意識し、「fashion tech newsを読んで、この商品が良いと知った」、「あのメディアの情報なら信頼できる」という状態をめざしてコンテンツ制作を行う日々だ。
現在の読者規模としては、月間PV数が平均で約250万、UU数がおよそ65万。ピーク時には300万PVを超えたこともあるが、編集部としては「まだ第一想起には届いていない」と考えている。ただし、数値はあくまで指標のひとつであり、記事の質とユーザー体験を落とさないことを重視している。
文/藏西隆介、取材/島田涼平(Digiday Japan)
撮影/増田義和
